-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
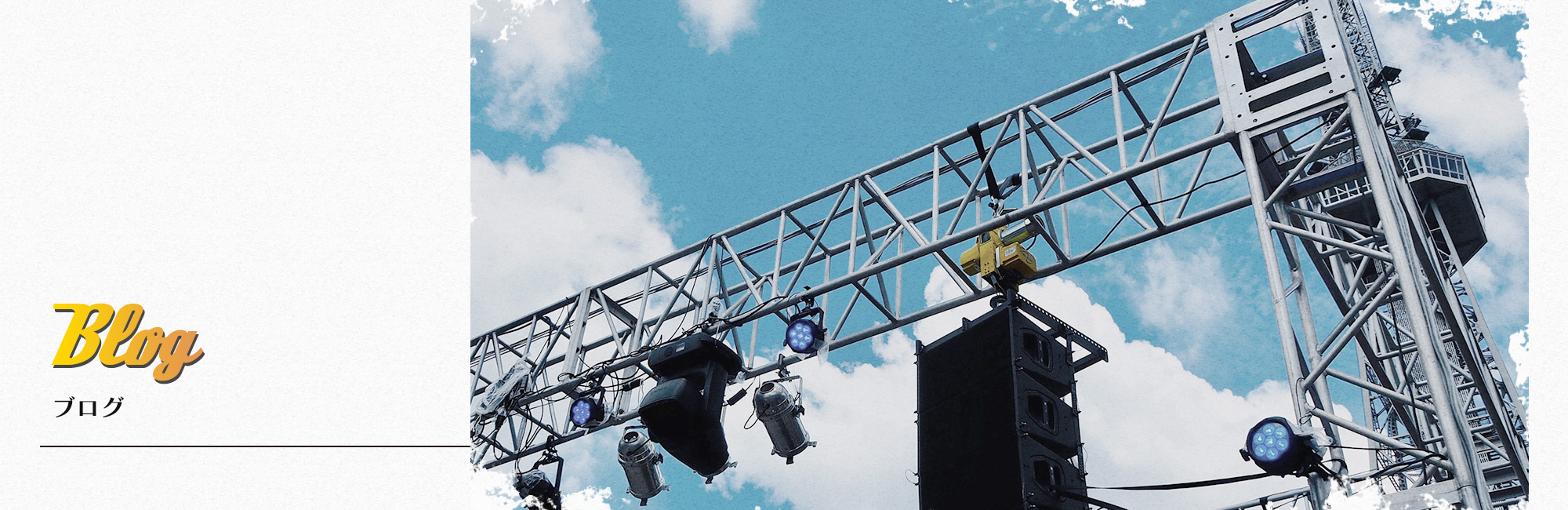
こんにちは!
一年目の西川です!
実は私、約三ヶ月前からとあるアーティストのツアーに参加させて頂いていたのですが、つい先日、無事に全ての公演を終えました!
舞台の飾り物がとても大きいのですが、僕にとっては大きな飾り物は初めてだったので、とても緊張しました・・・・
とはいえ、ツアーなので各会場同じセットを組むわけですから、二回目以降は流れを掴んだ状態なので、割とスムーズに設営できました。
初めて行う作業も多く、基礎から応用まで大道具としてのノウハウが詰まった舞台の内容であり、一度組んだ舞台をまた違う会場で組む機会というのはなかなか無いので、予習復習を現場で行えるとても良い経験ができたと思います。
本番中に舞台のセットを大きく変える「転換」もあったのでかなりメンタルも鍛えられました笑
僕にとっては中々大変な時期ではありましたが、今回の経験を経て、より一層成長できたと思っております。
これからも色んな現場に出向き、どんどん知識と経験を身につけていきます!
#大道具 #ライブ業界 #イベント #コンサート #千葉県 #千葉 #東京都 #東京
みなさんこんにちは!
株式会社Flapjackの更新担当の中西です!
さて今日は
flapjackのよもやま話~未来への展望~
ということで、今回は、近未来の大道具業界の展望について深掘りし、未来を形作る要素を解説します♪
目次
大道具業界は、舞台や映像、エンターテインメントの世界で欠かせない要素を担っています。観客や視聴者を物語の中に引き込み、没入感を提供する背景や装置は、時代の進化とともに大きな変化を遂げてきました。そして、近未来においては、テクノロジーの進化や環境への配慮が業界をさらに革新させるでしょう。
大道具の進化は、舞台や映画だけでなく、テーマパークや展示会、イベント空間にも大きな影響を与えます。観客の体験価値が向上し、エンターテインメント業界全体の発展を促進します。
近未来の大道具業界は、テクノロジーとサステナビリティを軸に、かつてないスピードで進化を遂げるでしょう。AIやロボティクス、デジタル技術の導入により効率化が進む一方で、環境への配慮や新しい表現手法の探求が求められます。また、大道具の可能性はエンターテインメントだけにとどまらず、教育や福祉分野にも広がりを見せるでしょう。
未来の大道具業界は、観客や視聴者に驚きと感動を提供するだけでなく、持続可能で多様性を尊重した新しい価値観を創出する存在へと成長していくに違いありません。
私たちflapjackでは自社の資材を使い丁寧に設営等を行っています!
そして、一緒に縁の下の力持ちになってくれる仲間を募集しています!
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
みなさんこんにちは!
株式会社Flapjackの更新担当の中西です!
さて今日は
flapjackのよもやま話~知られざる歴史~
ということで、今回は、大道具の歴史を深く掘り下げ、その変遷と重要性について解説します♪
舞台を彩る裏方の進化
大道具は、舞台や映画、テレビなどの演出において欠かせない存在です。物語の世界観を表現する背景やセット、道具は、観客に没入感を与える重要な役割を果たしています。その歴史は、古代の劇場文化から現代のテクノロジーを駆使した舞台美術に至るまで、舞台芸術とともに進化してきました。
1. 大道具の起源:古代劇場の舞台装置
① 古代ギリシャ劇場の大道具
背景画(スクエネ)と劇場設計
紀元前5世紀のギリシャ劇場では、背景画や簡易的なセットが使用されました。舞台背面の「スクエネ」と呼ばれる建物が、劇場の背景として機能し、その上に絵を描いて物語の舞台を表現しました。
機械的装置(メカネやエクサステロン)
メカネ(クレーン装置)を使って登場人物を空中に吊り上げる演出や、エクサステロン(舞台装置を回転させる機構)を用いたシーン転換が行われていました。
② 古代ローマ劇場の進化
豪華なセット
ローマ劇場では、ギリシャよりもさらに豪華なセットが作られ、舞台の奥行きや立体感が強調されました。
舞台装置の複雑化
移動式の舞台装置やトラップドアが導入され、ダイナミックな演出が可能になりました。
2. 中世ヨーロッパ:宗教劇と移動舞台
① 宗教劇と大道具
キリスト教劇の影響
中世ヨーロッパでは、教会が舞台芸術の中心であり、宗教劇が主流でした。大道具は、聖書の場面を再現するために使用されました。
固定舞台と移動舞台
固定舞台では舞台上に複数の「マンション」と呼ばれる構造物が並び、異なる場面を表現しました。一方、移動舞台では、ワゴン型のセットが各地を巡回し、宗教劇を広めました。
② 大道具の簡素化とシンボリズム
中世の大道具は、素材や技術の制約から非常に簡素でした。しかし、シンボルとしての意味が重視され、木の枝や十字架などで場面や物語を象徴的に表現しました。
3. ルネサンス時代:大道具の美術的進化
① 透視画法の導入
遠近法の革命
ルネサンス期には、透視画法が大道具の設計に取り入れられ、奥行きや立体感が演出されるようになりました。これは、バロック演劇において特に重要な進化でした。
シーンパネル(ウィング・アンド・ボーダー):
舞台の左右に設置されたパネルと、天井から吊り下げられた幕が、立体的な風景を作り出しました。
② イタリア演劇の影響
セバスティアーノ・セルリオの影響
建築家セルリオが舞台設計の手引書を出版し、大道具の構造が体系化されました。都市、森、宮殿など、特定のシーンに適したセットデザインが標準化されました。
4. 近代劇場と産業革命による進化
① ロマン主義と自然主義の影響
リアリズムの台頭
19世紀にはリアリズムの影響で、大道具は細部にまでこだわるようになり、現実の風景や建物を忠実に再現するようになりました。
自然主義の舞台
実際の家具や生活道具を使い、観客にリアルな生活空間を提示する演出が普及しました。
② 産業革命と機械化の進展
可動式装置
舞台床が上下するエレベーター装置や、回転舞台が開発され、大規模なシーン転換が可能になりました。
照明技術の進化
ガス灯から電気照明への移行により、舞台上の大道具がより鮮明に観客に見えるようになり、演出の幅が広がりました。
5. 現代の大道具:技術とアートの融合
① テクノロジーの活用
デジタル技術
プロジェクションマッピングやLEDスクリーンを使ったデジタル背景が、大道具の一部として活用されています。
モーションコントロール
自動化された舞台装置がプログラムによって動き、シーン転換がスムーズに行われます。
② 環境への配慮
サステナブルな材料
環境負荷を考慮し、リサイクル可能な素材やエコフレンドリーな塗料が使用されています。
再利用
一度使用した大道具をリサイクルして新しい舞台で活用する取り組みが進んでいます。
③ 新しい表現手法
インタラクティブな舞台
センサーやAR技術を利用し、観客の動きや反応に応じて舞台装置が変化する新しい表現が試みられています。
ミニマリズム
大規模なセットだけでなく、象徴的なアイテムや光を使って空間を表現するミニマリズムも注目されています。
6. 大道具の未来:新たな可能性
① AIと自動設計
AIがセットデザインを自動生成し、効率的かつ創造的な舞台設計が可能になるでしょう。観客のリアルタイムフィードバックを取り入れて演出を変化させるシステムも考えられます。
② バーチャルセットの融合
完全にデジタルなセットを使用した舞台や映画が一般化し、物理的な大道具とバーチャル背景が融合する新しい形態が生まれるでしょう。
③ 大道具の教育と保存
歴史的な大道具のデザインや技術をデジタルアーカイブ化し、次世代のクリエイターが学べる仕組みが整備されると予想されます。
まとめ
大道具の歴史は、舞台芸術の進化とともに歩んできました。古代の簡素な装置から、ルネサンスの透視画法、産業革命による機械化、そして現代のデジタル技術まで、大道具は観客を物語の世界に引き込むための重要な要素であり続けています。
未来の大道具は、テクノロジーとアートを融合し、観客の想像力をさらに広げる新しい形へと進化していくでしょう。これからも舞台芸術の裏方として、その可能性は無限に広がっていくに違いありません。
私たちflapjackでは自社の資材を使い丁寧に設営等を行っています!
そして、一緒に縁の下の力持ちになってくれる仲間を募集しています!
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
こんにちは!
一年目の西川です!
朝は冷え込み、すっかり秋になりましたね!
さて、今回は舞台における「転換」について書いていきます!
「転換とは?」
出演者様が舞台上で活躍する本番中、私たちは何をしているかというと舞台のセットや配置を変更する時間があります。(幕の振り落とし・楽器の移動等)
この時間を「転換」と言います。
転換は観客の皆様が見ており、かつ時間が限られているため、素早く、手際良く行わなければなりません。
失敗して公演に違和感を生んでしまうと、多くの関係者様、何よりお客様に多大なご迷惑をおかけしてしまいます。
トラブルなくスムーズに転換するためには、何度も何度も入念な打ち合わせによる変更とリハーサルを行い、公演に臨まならなければなりません。
大きな転換のある舞台では、一日の大半をリハーサルに費やすほど重要ななのです。
私たち大道具は舞台を仕込んで終わりではなく、本番に向けて転換の確認をし、より良い公演を行うために本番中も気を引き締めなければなりません。
転換はかなり緊張する一瞬ですが、リハーサル通りに進み一瞬にして姿を変えた舞台を見た時の、観客の皆様のリアクションを見た時はとても気持ちが良いです。
さて、今回は転換について書いてみました!
転換は、舞台からお客様のリアルな反応を間近で見ることができる貴重な機会ですね。
株式会社Flapjackでは、未来のイベント・コンサート業界を共に支える仲間を募集しています!
他の業界では味わえない経験や達成感を味わえるので、是非検討してみてください!
#大道具 #ライブ業界 #イベント業界 #コンサート業界 #千葉県 #千葉 #東京都 #東京
#求人
みなさんこんにちは!
株式会社Flapjackの更新担当の中西です!
さて今日は
flapjackのよもやま話~海外で大注目?!~
ということで、今回は、海外で注目される大道具の進化や、最新のトレンド、革新的な技術、そして成功事例について詳しく掘り下げていきます♪
大道具は、舞台芸術の中核を担う重要な要素です。
演劇、ミュージカル、オペラ、映画など、さまざまな表現の場で大道具は観客を魅了する空間を創り上げます。
近年、海外では伝統的な技術と最先端のテクノロジーを融合させた大道具が注目を集めており、クリエイティブな演出と技術革新が新しい可能性を切り開いています。
目次
大道具とは、舞台や映画のセットを構成する装置や構造物のことを指します。
背景や建物、家具、移動式の仕掛けなど、物語の世界観を具現化するために必要不可欠な要素です。
プロジェクションマッピングやLEDスクリーンを活用したデジタル大道具が増加しています。
分解可能で再利用可能な大道具が注目されています。
環境問題への関心が高まる中、持続可能な資材を用いた大道具の製作が進んでいます。
ロボティクス技術を活用し、動的な舞台演出が可能になっています。
観客との双方向コミュニケーションを可能にする技術が取り入れられています。
建物や背景に映像を投影し、リアルなセットをデジタルで表現する技術。
複雑な形状のセットパーツや小道具を短期間で製作可能。
俳優の動きをトラッキングし、大道具や映像にリアルタイムで反映。
舞台設計やリハーサルでの活用が広がっています。
大道具は、観客を物語の世界に引き込む魔法のような存在です。
海外で注目される新しい技術やトレンドは、舞台芸術の表現力をさらに豊かにし、観客の心を揺さぶる体験を提供しています。
持続可能性やテクノロジーの進化とともに、大道具はこれからも舞台芸術の未来を切り拓いていくでしょう。
私たちflapjackでは自社の資材を使い丁寧に設営等を行っています!
そして、一緒に縁の下の力持ちになってくれる仲間を募集しています!
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
みなさんこんにちは!
株式会社Flapjackの更新担当の中西です!
さて今日は
flapjackのよもやま話~魅力~
ということで、我々、大道具を扱う業種の魅力についてご紹介♪
大道具(だいどうぐ)の魅力について語ると、その独特な存在感と演劇や映画、テレビの舞台裏で果たす重要な役割が挙げられます。
大道具は、劇場や映像のセットにおいて物語の舞台をリアルに再現し、観客や視聴者を物語の中に引き込む力を持っています。そんな大道具の魅力を具体的に紹介します。
目次
大道具は、作品のテーマや舞台設定を物理的に表現するものです。
例えば、古代の宮殿や未来都市、自然の風景など、物語に合わせてあらゆる空間を再現することが可能です。
大道具がリアルであればあるほど、観客はその世界に没入しやすくなります。
また、セットの色彩や形状、質感などは物語の雰囲気を強調する役割も果たします。
大道具は視覚的に圧倒されるような美しさや迫力を持っています。
観客が最初に目にするのはそのセットですから、印象的な大道具は物語への興味を一瞬で引きつけます。
例えば、劇場での大きな城や、映画の中でのリアルな街並みなど、視覚的なインパクトは観客に強く残ります。
大道具製作には細部へのこだわりが必要です。
実物に見えるように木材や金属、布などを加工し、特殊なペイント技術を使って年季の入った家具や建物のように見せたり、リアルな汚れや傷を再現したりします。
こうした手作業には高度な技術が必要で、舞台美術家や職人の手腕が光ります。
大道具は単なる背景ではなく、俳優の演技にも影響を与えます。
例えば、階段を上がる音や、扉を開ける感触などがリアルであることで、俳優がより自然に役に入り込むことができ、観客にもそのリアルさが伝わります。
大道具が物語の一部として機能することで、俳優と観客の間にリアルなつながりが生まれます。
大道具は、現実世界には存在しないものも作り上げることができるのが魅力です。
たとえば、魔法の世界や未来のテクノロジーを駆使した都市など、想像の中だけに存在する空間を具現化することで、観客は普段の生活では経験できない世界を体験できます。
大道具の制作には、舞台美術家、セットデザイナー、大道具スタッフ、技術者など、多くの人々が協力します。
各分野の専門家が一丸となって一つのビジョンを実現するプロセスは、クリエイティブなチームワークの素晴らしさを表しています。
この協力があるからこそ、観客に感動を与える大道具が完成します。
大道具は、観客を物語の世界へ引き込み、想像力を刺激する力を持っています。
俳優や物語のための「舞台」として欠かせない存在であり、そのリアリティと美しさが観客の記憶に深く刻まれるものです。
縁の下の力持ちとはこのことかもしれません!
私たちflapjackでは自社の資材を使い丁寧に設営等を行っています!
そして、一緒に縁の下の力持ちになってくれる仲間を募集しています!
お問い合わせはお気軽に♪
![]()
こんにちは!
一年目の西川です!
日々、私たちはプロとして様々なイベント・コンサートの舞台を作り上げています。
安心・安全な施工を心がけ、観客の皆様からみて見栄えの良い舞台を作り上げるには、常に意識しなければならないことがたくさんあります。
今回は、そんな舞台美術の施工においてよく聞く大事なポイントを3つご紹介します。
1.安全な舞台作り
舞台設営において最も大事なのがやはり安全性。
自立している部材が倒れてこないか、
人が通る導線の足元に物を置いていないか、
釘やビスといった怪我の元となる物が落ちていないか、
上に吊り上げる物に落下物が乗っていないか、
などなど、四方八方あらゆる場所に危険が紛れている可能性があるので、常に視野を広げながら作業を行わなければなりません。
周りの人を思いやりながら仕事をすると言う点では、全てにおいて通ずることですね!
2.段取り
舞台設営に使用する部材はどうしても大きく、スペースをとってしまう物が大半です。
イベント会場では時間と場所が限られています。
作業員も多く、他のセクションの方の物も置いてある中で部材をどのように置き、どのような順番で手をつけていくかが仕込みの効率を上げる鍵となっています。
大きいものを長時間同じ場所に置いてしまっては他の人の邪魔になり、
最悪の場合事故や怪我の原因となってしまいます。上に書いた安全な舞台作りと繋がりましたね。
必要な物をどのように置いて、どの順番で作業をしていくかを事前に確認しておくことが、安全かつ効率よく舞台作りを行う上で重要ということですね!
3.美しく観せる
安全性、効率と紹介していきましたが、やはり最も大切なのが「見栄え」です。
私たちの仕事はかっこよく、綺麗な舞台を作りお客様に非日常をお届けすることです。
優先順位をつけるわけではないですが、私たちの仕事の根本と言える部分なのです。
例えばピンと張らなければならない幕がシワになっていないか、木材でできた飾り同士をつなぐ際にずれていないかなど、お客様がライブに没頭する上で違和感がないか気にしなければなりません。
観客の皆様がお金と時間を割いて足を運んで下さって来ている訳ですから、失望させるわけにはいきません。
自分が設営に携わった舞台が完成した時、お客様を熱狂させた時、笑顔で帰るお客様を見た時、この時に感じる達成感こそ、このイベント・コンサート業界の醍醐味だと思います。
今回は舞台設営の3つのポイントを紹介しました!
今までこの業界で働いてきてよく聞くポイントを個人的にまとめたものですので、人によって違う部分もあると思いますが、今回は僕自身のメモのようなものだと思ってください。
今後も上記の3つのポイントを意識して、よりかっこいい業界人になります!!
よろしくお願いします!!!!!
#大道具 #ライブ業界 #イベント業界 #コンサート業界 #千葉県 #千葉 #東京都 #東京
#求人
こんにちは!
一年目の西川です!
普段舞台を設営している私たちは、業界において「大道具」と呼ばれています。
様々な道具を使い釘を打ったりボルトを締めたりと、大工に近い作業を行なっているのですが、実は物を組み上げる過程で決定的な違いがあります。
今回はそんな大工と大道具の違いについて話します。
大工が組み上げる家具や建物などに求められるのは、やはり強度です。
生活の中で長期にわたって使うわけですから、何十年、何百年と壊れにくい物を作り上げる必要があるわけです。
返って舞台美術において求められるのはバラシやすさです。
現場では時間が限られているので、表に見えている部分とは違って、裏側は案外シンプルな構造になっています。
壊れにくい物を作り上げる際は複雑な構造にする必要がありますが、こと舞台美術においては、見栄えが良く分解しやすければ良いわけですね!
危険性のない部分の釘を打つ際は頭を出して抜きやすくするといったこともしています。
バラシの際に幕などを釘で深々と打たれている釘を取るときは、かなりめんどくさいです….笑
今回は大工と大道具の違いについてご紹介しました。
私たちにとって違いのわからない仕事でも、実際にこういった微妙な違いがあると思うとまた見る目が変わりますね!
#大道具 #ライブ業界 #イベント #コンサート #千葉県 #千葉 #東京都 #東京
こんにちは!
一年目の西川です!
実は、西日本と東日本で電気の周波数が違うってご存知でしたか?
そもそも電気における周波数って何かというと、簡単に言ってしまえば一秒間あたりに電気の+と−が入れ替わる回数のことです。
この周波数が東日本では50Hz、西日本では60Hzとなっています。
これが私たちの生活にどう関わってくるかというと、東日本・西日本間で引越しをした際にその地域に対応した周波数の電化製品を使わないと、故障の原因になる場合があります。
大抵の電化製品は周波数が変わっても使える場合が多いですが、念頭に置いておくと良いですね!
実は、この地域による電気の周波数の違いがイベント業界に影響を及ぼすこともあります!
私たちは普段、モーターと呼ばれる機械を操作することによって、舞台の装飾やその他重量物を吊っています。
地域が変わって電気の周波数も変わると、モーターの操作感が違うんです!
一例として、本番中にモーターを使って大きいパネルを動かすライブがあったとします。
東日本で練習して西日本の会場でいざ本番!となると、パネルの位置が微妙にズレてしまったりするわけです….
なので前回と周波数が違う会場であった場合、モーターのボタンを押す時間を変えなければなりません。
練習なしでぶっつけ本番!ではなく何度も何度も確認を重ねることで、安心・安全に本番を迎えることができるわけです!
長々となってしまいましたが、電気の周波数とイベント業界の意外な関係について紹介させていただきました!
#イベント #コンサート #ライブ業界 #千葉 #千葉県 #東京 #東京都
こんにちは!
一年目の西川です!
普段より、様々なイベントの舞台設営に携わっている私たちですが、
中には野外で行われるイベントを設営することもあります。
春夏秋冬、暑い中、涼しい中、自然に囲まれながら開放感あふれる場所で一喜一憂するイベントも楽しいですよね!
先日もとある野外現場の施工に携わってきました。
序盤は雨が降り続け、足元も悪いため徐々に足が痛くなってきました。
正直環境としては最悪なため、いつまでこの状況が続くのかと不安になってきます。
中盤に差し掛かり着々と舞台が出来上がっていく中、
作業に夢中になっていた顔をふと上に見上げると、さっきまで濁っていた空が深々とした青色に染まっていました!

こちらがその様子です!
この空を見た瞬間に、今までの疲れが一気に吹き飛びました!
現場によっては、このような素晴らしい環境で仕事ができるのもイベント・コンサート業界の良さの一つでもありますね✨
株式会社Flapjackでは、一緒に働く仲間をまだまだ募集中です!
・仕事を覚えて成長を実感する喜び
・カッコイイ舞台を作り上げた時の達成感
・他の業界では感じられない楽しさ
共に感じてみませんか?
少しでも気になった方はぜひお問い合わせください!
#イベント #コンサート #ライブ業界 #千葉 #千葉県 #東京 #東京都